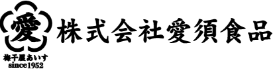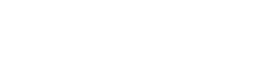南高梅について
南高梅のルーツ
和歌山県の旧・上南部村(現在のみなべ町)で、村長の長男として生まれた高田貞楠(たかだ さだくず)は、明治35年、自らの桑畑を梅畑へと転換し、梅の栽培を始めました。やがて彼は、ひときわ大粒で紅をさす、美しい実をつける一本の木に出会います。この木は「高田梅」と名付けられ、彼の手で母樹として大切に育てられました。
時は流れ昭和25年、地元・南部川村では、数十種におよぶ梅の中から最も優れた品種を選ぶため、5年にわたる調査が実施されます。その調査で風土との相性や品質の安定性が高く評価され、最優良品種として「高田梅」が選定されました。この調査には、地元の南部高校(通称・南高)の教員と生徒たちも参加し、品種選定に大きく貢献しました。
こうして、「南部」の“南”と「高田梅」の“高”を組み合わせた「南高梅(なんこううめ)」という名が生まれます。南部高校の尽力もその名に刻まれ、昭和40年には正式に種苗登録。以来、南高梅は日本を代表する梅の品種として高く評価され続けています。

南高梅の特長は、皮が薄くてやわらかく、果肉は厚くジューシーで、種が小さいこと。さらにミネラルを多く含み、味わいにも優れており、梅干しには最適とされています。
その背景には、みなべ町ならではの自然条件があります。黒潮の影響による温暖な気候、そして「瓜渓累層(かけいるいそう)」と呼ばれる地層に多く含まれる炭酸カルシウムがもたらす中性の土壌――これらが南高梅の品質を根底から支えているのです。
梅干しができるまで

開花
早春二月半ばになると、山々が花の帯で包まれ私たちを小さな白い花と甘酸っぱい香りで楽しませてくれます。

収穫
暖かくなるにつれて梅の実はふくらみ、梅雨の頃には収穫を迎えます。町は一年で一番忙しい時期です。
青梅としても出荷され、梅酒・シロップ・ジュース・ジャムなどに利用されます。ここでもみなべ町産の大粒、肉厚の梅は人気があります。

塩漬け
6月に収穫された梅は良質の梅だけを厳選し洗浄選別後、タンクで約2ヶ月以上塩漬けされます。塩漬けされた梅がタンクから取り出されたところ。まだ黄色いです。

天日干し
「土用干し」ともいい、真夏の炎天下43度まで上がる熱気ムンムンのハウス内で6〜7日間干しあげます。
裏表がむらなく干しあがるように、人手で返します。

樽詰め
干しあがった梅はサイズ毎に分けられ樽に詰められます。樽づめされた梅を6ヶ月以上じっくり寝かせます。

出荷
肉厚で皮が柔らかな南高梅の加工や箱詰めは、手作業で行っています。減塩・調味された食べやすい梅干しとしてさまざまな商品に加工し販売しています。